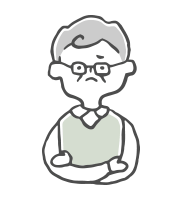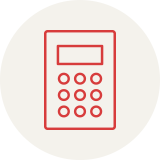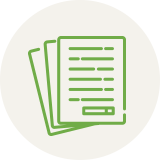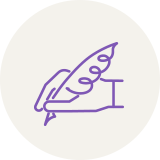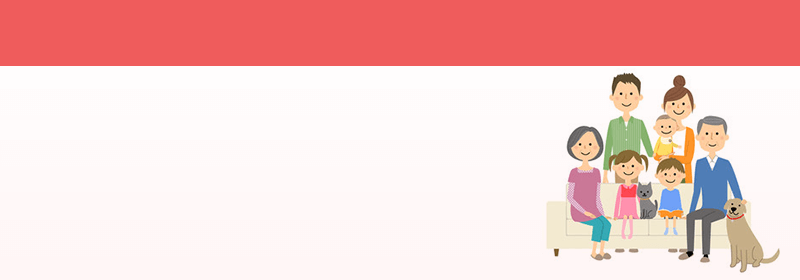遺留分制度の見直しについて
遺留分制度の見直しについて
2019年7月から遺留分制度が変わりました。
この記事では遺留分とは何か、法改正によって何が変わったのかを専門家が解説します。
遺留分制度とは
そもそも「遺留分」とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保証されている相続分のことで、亡くなった方が遺言を残していた場合に考えなくてはいけない法定相続人の権利です。
例えば、被相続人(亡くなった方)が遺言書に「長男のAに全財産を相続させる」と記載されていた場合、遺言書通りに遺産を分割すれば長男のA以外は財産を受け取ることができなくなります。
被相続人の財産をまったく相続できないとなると、他の相続人たちは生活を維持できなくなる恐れがあるため、財産の一定割合を相続する権利が保証されます。それが遺留分です。 (また、その遺留分に満たない財産しか相続できない場合、その不足分を請求することを改正前は遺留分減殺請求といい、改正後は遺留分侵害額請求といいます)
遺留分の割合
遺留分はどれくらい保証されているのでしょうか。
遺留分は、法定相続分の1/2です。
この法定相続分ですが、相続人の組み合わせ人数によって異なります。
例えば、配偶者1人・子ども1人の場合、それぞれ法定相続分は、配偶者1/2・子ども1/2です。そのさらに1/2の割合にしたものが遺留分です。つまり配偶者1/4・子ども1/4です。
遺留分制度の問題点
改正前の遺留分制度には問題点がありました。いくつかあるうちの2つをご紹介します。
①遺留分減殺請求権の行使によって共有状態が発生する
被相続人Aさんは、財産のほとんどを自宅などの不動産として所有していました。Aさんには子どもが2人(長男B、次男C)いますが、Aさんは「全ての財産を長男Bに相続させる」との内容の遺言書を作成し、亡くなりました。この場合、次男Cは遺言の内容により一切の財産を取得できませんが、法律上、遺留分を有しています。改正前の民法(2019年6月30日まで)では、遺留分侵害があった場合、遺留分権利者(次男C)は遺留分減殺請求を行うことができ、その請求が認められると、不動産であっても遺留分割合に応じた持分が次男Cに移転することになります。 例えば、相続財産が5,000万円相当の不動産のみで、法定相続人が子2人の場合、次男Cの遺留分は全体の4分の1、すなわち1,250万円相当となります。改正前は、この1,250万円分を「現金で請求」することはできず、不動産の4分の1の持分を取得することとなり、不動産が共有状態となってしまう点が実務上の大きな問題でした。
②共有割合は大きな額になることが多い
共有割合は、不動産の評価額を基準にして決まるため、大きな額になることが多いです。
そのため、持分権の処分に支障が出る恐れがあります。
改正後(2019年7月1日施行)のポイント
遺留分制度の見直しによって、変更となった点を解説します。
①不動産の共有状態を回避できる
遺留分を侵害された者は、遺贈や贈与を受けた者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の請求をすることができるようになりました。
言い換えれば、不動産を遺贈や贈与で受け継いだものは、金銭を支払えば不動産を共同で所有する必要がなくなります。
これにより不動産の権利関係が複雑化することを避けることができます。
②遺留分侵害額請求に対する支払いの猶予
遺贈や贈与を受けた者が金銭を直ちに準備することができない場合には、裁判所に対し、支払期限の猶予を求めることができるようになりました。
この記事の執筆者

- エスペランサグループ 代表社員 税理士 吉田 博幸
-
保有資格 税理士 経歴 岡崎・名古屋・豊川など愛知県下に4拠点を展開する税理士法人エスペランサの代表社員。平成2年税理士登録以降、数多くの税務相談、相続・事業承継案件に取り組む。平成26年には、名古屋駅に資産税専門の「相続ラウンジ」を開設し、相続や事業承継支援で高い評価を得ている
また、資格専門学校の税理士講師も30年以上歴任し、後進の指導にも力を入れている。
- オンライン
相談可能! - 愛知県外の方も
ご相談可能! - 相続の
専門家が対応! - 無料相談はこちら
ご相談の多いメニュー
家族信託をお考えの方へ
終活・相続のご相談は当相談窓口にお任せください
よくご覧いただくコンテンツ一覧
岡崎・安城・刈谷で
終活・相続に関する
ご相談は当事務所まで